最新のお知らせ
| 過去のお知らせ |
フェスタ終了!みなさんありがとうございました。
投稿日時: 2017-10-29 17:12:49

みなさんこんにちは。
台風も過ぎて青空が見えてきました。
みなさんお住まいのあたりは雨の被害は大丈夫でしたでしょうか。
本日開催された医療介護フェスタは15時をもって終了しました。
台風による大雨にもかかわらず、
約600人もの方にご来場頂きありがとうございました。
和気中学校吹奏楽部のコンサートに始まり、
血糖、血圧、肺年齢などの検査、
子どもさんに大人気だった看護師体験、指の型どり、革細工作りなどの体験ブースには
たくさんの人が集まっていました。
午後から行われた清麻呂太鼓のズドンと響く力強い演奏にはみなさん聴き入っていました。
昨年の大混雑を反省して、
今年は整理券を配布する形をとったため、
あまりお待たせすることなく皆様に見て頂けました。
アンケートでも楽しかったという声をたくさん頂きました。
あいにくのお天気ではありましたが、
多くの地域のみなさんと直接ふれあうことが出来て
良いイベントとなったように思います。
これからも北川病院並びにエスペランスわけをよろしくおねがいいたします。
医療介護フェスタ開催中です!
投稿日時: 2017-10-29 12:20:29

みなさんこんにちは。
今現在当院とお隣のエスペランスわけで医療介護フェスタを開催中です!
あいにくのお天気にもかかわらず多くの方にご来場頂いています。
午後は12時半から清麻呂太鼓の演奏があり、
13時半からはエスペランスで講演会も行います。
15時まで各種検査や体験も行っておりますのでぜひお越しください。
午後からは待ちが無くすっと検査ができるかもです!
スタッフ一同お待ちしております!
フェスタやります!
投稿日時: 2017-10-28 14:30:36
みなさんこんにちは。
今週も台風が近づいて朝からいやなお天気ですね。
明日29日の医療介護フェスタですが、
大雨が降っていてもやります!
みなさん是非来てみてください!
みんなでウォーキング
投稿日時: 2017-10-26 15:30:19
みなさんこんにちは。
今日は看護部による健康教室があり、
参加者と職員で病院裏の片鉄ロマン街道を歩きました。
出発前に血圧、血糖値の測定をし、
リハビリの岡田室長に教わった体操で準備運動をしてから出発です。

今日は絶好のお散歩日和で、
みなさんそれぞれのペースで益原の交通公園のあたりまで歩きました。
通り沿いの草花や、公園に遠足に来ていた元気な子ども達を眺めながら、
良い運動になりました。
病院に帰って血糖値を測ってみるとびっくりするほどいい数値になっていた方もいて、
運動の効果がしっかりと現れていました。
やはり健康のためには運動は欠かせませんね。
下の写真はいつも参加されている方が描いた絵はがきです。
とても上手で良い絵だっだので写真を撮らせていただきました。

さて、いよいよ今度の日曜日は
北川病院、エスペランスわけ合同の
医療介護フェスタが開催されます。
ただ台風が心配なところですがなんとか天気が持ってくれることを祈るばかりです。
1日塩分量測定
投稿日時: 2017-10-11 16:43:19
みなさんこんにちは。
突然ですが、昨日1日のうち、何を食べましたか?
その食べ物に含まれている塩分量がだいたい何グラム程度なのか知っていますか?
塩分なんか気にした事がない、という方ももしかしたらおられるかもしれませんが、
実は食べ物には多くの食塩が含まれているのです。
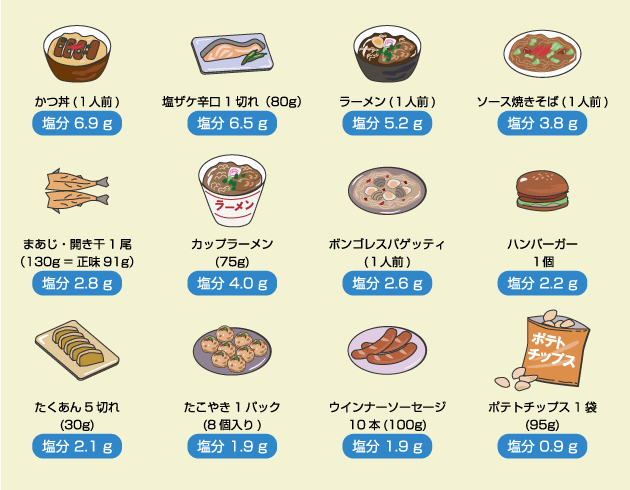
全国健康保険協会HPより引用
この摂取した食塩の大部分は尿として体の外に排泄されます。
ですので、尿中に含まれる塩分排泄量を調べることで、
1日の食塩摂取量を推定する事ができるのです。
1日の塩分摂取量の目標値は、健康な男性で8g未満、女性で7g未満、
高血圧の治療をする人で6g以下といわれています。(日本人の1日塩分摂取量の平均は約10.4g)
塩分を摂りすぎると、むくみや高血圧、腎臓疾患になりやすくなるため、
毎日の食事を今までよりも少し薄味にするなど、減塩に心がけましょう。
今月末に行われる「北川病院&エスペランスわけ 医療介護フェスタ2017」でも、
実際に尿を採ってもらい、自分が昨日1日で摂った塩分の量を知る事ができる体験を企画しています。
(混雑防止のため整理券を配布します)
他にも普段は経験する機会が少ない、健康・福祉に関する体験をすることができます。
詳しくはこの『病院からのおしらせ』で先月紹介しました「医療介護フェスタ2017開催!」をご覧下さい。
お時間があればぜひ、10月29日に開催される 北川病院&エスペランスわけ 医療介護フェスタ2017に
足を運んでみてください。